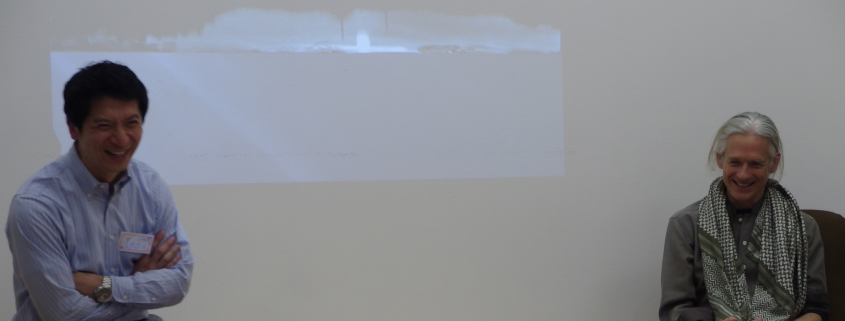
【第三の道】 本当の強みは単一性ではなく多様性 現代の「まれ人」が語る日本文化の特色 エヴァレット・ブラウン氏(写真家)× キム・インス
今回の「第三の道」は、アメリカ生まれの写真家、エヴァレット・ブラウン氏をゲストに迎えた。湿版光画(写真)という古典的技法で、日本の美を表現するエヴァレット氏。現代の「まれ人」が語る日本論は「女子高生にも連綿と引き継がれる匠の精神」「日本の本当の強みは単一性ではなく多様性にある」など、日本らしい「第三の道」を探るため、刺激に満ちた内容だった。
日本人が祖国を誇りに思うのが、うらやましい
ファシリテーターを務めたCCCパートナーのキム・インスは、日本で生まれ育ったが朝鮮半島にルーツをもつ。「私は教育の影響もあって、日本とは違う国を祖国だと思って育ってきた。そして多くの日本人が自分の祖国を誇りに思っていることを、うらやましいなと感じていました」と、インス。ところがエヴァレット氏と出会い、「なんだ、この自由な感じは」と思ったという。自分が生まれたわけでもない国を高らかに誇り、『日本力』という本まで書いてしまう。「そんなエヴァレットさんのお話の中には、自分が乗り越えたいとおもっていることの糸口が、いくつか転がっているのではないか。そう思ってここに座っています」と話し、エヴァレット氏の話を促した。

エヴァレット氏は今日の話の重要テーマの一つとして、「まれ人(びと)」の説明から話を始めた。「まれ人とはよそからやってくる人、神のことです。例えば七福神は、その一例です」と話し、日本の文化や社会をさかのぼっていくと、まれ人が果たす役割は非常に大きなものだったと説明。「現代は多様性のある社会が大きなテーマとなっているが、昔の日本では、まれ人の存在が社会の多様性を生みだすために重要だったのです」
縄文土器とデコ携帯は、「どうみても同じ」
今回のキーワードとして「まれ人」「多様性」を提示したエヴァレット氏。ここから話題は日本文化の特徴へと移っていった。「日本人のルーツは、最近とても興味深いテーマ」というエヴァレット氏がプロジェクター画面に映し出したのは、縄文土器と、ビーズやガラス玉でデコレーションされた“デコ携帯”だった。「このデコ携帯の持ち主は、原宿をよく歩いているという女子高生です」。両者はどう見ても同じだと説くエヴァレット氏。「だってここまでやらなくていいでしょう(笑)」。デコ携帯はただの携帯電話ではなく、女子高生が自分の世界を、そこに吹き込んでいるというのだ。「それは匠の精神。ただモノを作るのではなく、モノを特別な何かにしてしまう。そんな精神を女子高生だけでなく、多くの日本人が受け継いでいます」
縄文土器とデコ携帯の写真を並べて見せながら、エヴァレット氏は「他の民族なら、こういう道具をもっとシンプルに作るのではないでしょうか」と話した。そして来場者に、「とても美しい、よく作り込まれた道具と、単にシンプルで、さほど美しくはない道具。あなたならどちらを仕事に使いたいですか」と問いかけた。
美しい道具は、触れているだけで楽しくなる。すると仕事も楽しくなってくる。「仕事をしながらインスピレーションが湧きやすくなり、道具を大事にするようにもなります」。だがシンプルな道具ではこうはいかない。「そんな道具を使ってもやる気は出てこないし、あまり大事にしないかもしれません」
また他の場所からやってきた人が、その美しい道具を目にしたらどうなるだろうか。ひょっとするとその美しさに共感して、欲しがるかもしれない。「美しいものを見て共感する。これは文化の原点です。また、縄文時代にその道具が求められたなら、物物交換が始まるかもしれない。そこには経済も生まれます」。縄文時代から連綿と続く、日本人の美しい道具への心遣い。「そこに注目すると、現在下り坂な日本の経済も、まだまだ捨てたものではないと感じます」とエヴァレット氏は語った。
エヴァレット氏は3年前まで、通信社のカメラマンの仕事をしていた。「ですが日本を表現するには、デジタルカメラではダメだと思いました」。日本の独特な空気感を表現するのは、デジタルでは難しかったというのだ。こうしてエヴァレット氏は、湿版写真という江戸末期から明治にかけて使われていた、古典的技法を学んだ。「写真という漢字が使われる前、それは光画と呼ばれていました。私も自分の作品を光画と呼んでいます」
湿版光画(写真)はガラス板に感光剤を塗ってネガにし、それをカメラに入れて撮影する。薬品のすすぎ方によって意図的にいろいろな模様を入れることができる。「一枚一枚、まったく違う作品に出来上がる。写真より焼物や日本画に近い技法だと思い、ハマっています」
最初の人類の記憶も、アフリカの草原に残る
湿版光画で「日本の雅」「匠」など様々なテーマの作品を手がけるエヴァレット氏。ここでは「おもかげ」に関するお話を紹介しよう。エヴァレット氏がいう「おもかげ」とは、歴史のある場所に潜んでいる記憶のことだ。「20年くらい前に、南アフリカの自然科学者、ライアル・ワトソン氏と交流したことがありました」。アフリカ生まれのワトソン氏に言わせれば、12万年前の最初の人類の記憶も、現在のアフリカの草原には残っているのだという。「昔の音楽家、詩人、ダンサー、呪術師らは、土地に潜む先祖の記憶を感知し、表現していたのだと語っていました」
この話を聞いてエヴァレット氏が思い起こしたのは、日本の寺や神社で感じられる、独特な空気感だった。「神社や寺の歴史を調べると、過去に残酷な出来事があった場所もあり、それが理由で神社や寺が建っていることがあります」。このように昔の人たちの記憶は、日本でも至る所に残っている。湿版光画という技法を通じて、その場所に潜む記憶を呼び起こそうとしているのだと、エヴァレット氏は自分の取り組みを説明した。
エヴァレット氏は山伏に興味をもち、自身でほら貝を吹いているが、それも土地に残る「おもかげ」と関係しているという。「山伏がほら貝を吹くのは、その場所に潜む記憶を、呼び起こそうとしているのです」。その土地の歴史を思いながらほら貝を吹くと、響きが戻ってくる。「土地が発する響きを素直に受け取って光画を撮影すれば、思いがけず面白い作品ができ上がります」
ところが現代の日本人は、「土地に潜む記憶を聞きだす力」が弱まっているのではないかと、エヴァレット氏は指摘する。かつての日本には農民が多く、より多くの情報を自然から求めていたから、土地に潜む記憶を聞き出すことにも長じていたのだろう。「現代はそんなことをしなくてもグーグルで十分でしょ? 果たして本当にそれでいいのか、少し疑問を感じますが」
突然、原種に戻ってしまう「先祖がえり」
次にエヴァレット氏は、「先祖がえり」について話し始めた。「植物の品種改良では、改良した品種を何世代が植え続けると、ある世代で突然、原種に戻ってしまうことがある。酵母でも同じような現象が起こるといわれています」
こうした現象は先祖がえりと呼ばれているが、日本社会にもこの先祖がえりが起こっていると、エヴァレット氏はいう。「例えばかやぶき屋根の職人。年長の職人には、もうこの仕事は自分の代で終わりだという人が多い。ところが、実は若い人がかやぶき職人の世界に入ってきている。特に女性職人が増えています」。庭師の世界では水琴窟という仕掛けで、先祖がえりが見られるという。水琴窟は手水鉢の下の地中に甕を逆さに埋めた空間を作り、そこに水を滴らせることできれいな音を響かせる仕掛けだ。江戸期から明治にかけて茶人の間で流行ったが、戦後はあまり見られなくなっていた。「最近また手がける職人が増えて、復活してきています」。藍染、和紙づくり、山伏の世界などでも先祖がえり現象が起こりつつあると、エヴァレット氏は紹介した。
日本人のルーツはどこからやって来たのか
「先祖がえり」とはつまり、日本人のルーツにさかのぼることを意味するが、ここで話題は、日本人のルーツはどこからやって来たのかということに移っていった。「東大でDNAを調べている研究者の話によると、平均的な日本人のDNAは、25%が朝鮮半島系、中国系も25%、12.5%はアイヌなど北方系、同じく12.5%が沖縄系、残る25%は中央、西、東南などアジア各地に先祖をもつということでした。そうだとすると皆さん、日本人はよくいわれるように、単一民族だと思われますか?」と、エヴァレット氏は問いかけた。
「少し調べると、日本人が単一民族だという主張は、明治時代から目立ち始めたことがわかります」。欧米列強と対等に付き合っていくため、「日本も一神教の国である」とアピールするために国家神道が形成された。また統一国家であると主張するために単一民族が強調されたというのだ。「実際、江戸時代までの日本人は、日本国の一員という意識より、藩や村の一員という意識の方が強かったようです」
日本列島に流れ着いた、多様な人たちが作った
はるか昔から日本列島に存在した単一の民族というよりは、世界各地から日本列島に流れ着いた、多様な人たちが作ってきたのが日本という国なのではないか。「そう考えると、日本の本当の強みは多様性ではないでしょうか」とエヴァレット氏は語った。そんな見方を裏付ける話を、東大寺の僧から聞いたとエヴァレット氏は紹介する。「奈良時代、東大寺が完成した際の式典には、朝鮮、中国、ベトナム、インド、中東、東南アジアなど世界各地から2万人が集まったといいます。正倉院には主にシルクロードを通って日本にやって来た世界の宝物がありますが、渡来したのは文物だけではなく、人もやってきたのです」
海を越えて、世界各地から日本に流れ着いた人たち。「彼らは危険な旅を生き残った、強くて、優秀で、運がいいといえます」。エヴァレット氏は自らの経験として、日本は水が良く、食べ物も美味で温泉もあり、一度滞在してしまうと海外の元いた場所に帰りたくなくなると話した。「昔日本にやってきた“まれ人”たちも、日本で一冬越したら、帰りたくなくなったことでしょう」

ここまでのエヴァレット氏の話を受け、インスは「お話で印象に残ったのは、日本は東アジアの人種のるつぼであり、本当の強みは多様性にあるということ」と感想を述べた。そしてここから、エヴァレット氏が提示した話題について、さらに探究を深めていこうと来場者に呼びかけた。インスが最初に話題にしたのは日本文化の「わびさび」だった。「事前の打ち合わせでも話題になり、興味深いお話になった。改めて、わびさびとはなんでしょうか」と、エヴァレット氏に問いかけた。
「本当のわびさびを体験したいなら、韓国に行け」
エヴァレット氏は京都の帯問屋、山口源兵衛氏から「本当のわびさびを体験したいなら、韓国に行きなさい」といわれたことを紹介。「茶道がわびさびを取り入れたのは、朝鮮の生活雑器を茶碗に見立てた、井戸茶碗などから影響を受けています」。民衆的工芸品の美を称揚する「民藝運動」を展開した柳宗悦の著書を読むと、そうした話が多数紹介されていると話した。
この話を聞いたインスは「何度も韓国には行っているが、何も感じない」と応じて会場の笑いを誘った。デジカメ一台持って、韓国のわびさびを撮影するツアーを企画しようと呼びかけ、エヴァレット氏や来場者の賛同を得ていた。
来場者の一人は、「民藝の美について柳宗悦が言っているのは、美しいものを作ろうと狙って作るのはダメだということ」と話した。生活の中で、無心に作られたものが、実は美しかったということが起こる。「雑器づくりも突き詰めていくと、どこかから別の力が降りて来て、ものすごい美が宿ることがあるのです」。エヴァレット氏の湿版光画は自力と他力の追究という意味で、美を宿した雑器づくりと相通じるのではないかと語った。
こうした見方を受けてエヴァレット氏は、「確かに撮影の準備には最善を尽くす」と応じた。ただ、湿版光画の写真機にはシャッターはなく、ふたの開け閉めで露光時間を決める。「ふたを開けたら、あとはお任せ。10分から20分、その場から離れる。私の思いがその場の空気を邪魔しないためです。これはまさに他力だと思う」と説明した。
この話に能の世界からの見方を付け加えたのが、来場していた能楽師の武田宗典氏だ。武田氏は自身も第8回の「第三の道」で語り手を務めている。能の舞台もそれぞれの出演者がベストを尽くして事前の稽古をする。「ですが本番前の通し稽古は、あって一回。私が明日出演する舞台はリハーサルなしの一発勝負。ジャズのセッションのようなものです」と武田氏。そこにそれぞれのお客の思いが重なることで、一人ひとり、同じ演目でも全く違うものを感じ取れるといい、「エヴァレットさんの話と相通じる」と語った。
米国生まれで日本に定住したエヴァレット氏は、現代の「まれ人」と呼んでいい存在だろう。「よそからやって来た人」の日本文化への視点は、私たち日本人にとっても「目からウロコ」の連続だった。自らの本当の姿を把握するには「まれ人」の視点が欠かせないことが、実感できた時間だった。
エヴァレット・ブラウン
1959年、アメリカ生まれ。1988年から日本に定住し、EPA通信社日本支局長などを務めた。湿版光画という古典的な写真技法で、日本の面影や匠精神を表現する。国内の媒体を始め、「ナショナル・ジオグラフィック」「家庭画報INTERNATIONAL」などに作品を寄せている。著書は『俺たちの日本』(小学館)『日本力』(松岡正剛氏との共著、パルコ出版)など多数。















